|
||||||||||||
|
||||||||||||
�Г����i�u�V���[�Y�A�h�o�C�U�[�v���x���X�^�[�g�@�`���_�i�����E������j�̏��q�͊��p�̓����́A��N����ڋq�̖ʂŋ�̉����Ă���B��N10������A�Г����i���x�ł���u�V���[�Y�A�h�o�C�U�[�v�̃e�X�g���J�n���Ă���B�����x�́A�̔����Ƃ��Ă̐g�����Ȃ݂�ڋq�̊�{����A�ԓx�A�Z�p�Ȃǂ���A�C�̏��i�m���A�t�b�e�B���O�Z�p�܂Ŕ̔��ɕK�v�Ȋ�{�I�Ȃ��Ƃ��w�сA�������s���Ď��i��^������́B���Ɏ��Z��K�{�Ƃ���u�V���[�Y�A�h�o�C�U�[�E�}�X�^�[�v�ւƐi�ށB���̐��x�́A���ƌC�ƌ��N���c��(�e�g�`)���F�肵�Ă���u�V���[�t�B�b�^�[�v�擾�҂̑����{��ɂ��ʒu�t���Ă���B ���Ђł͒���I�ɍs����ڋq���C�͂Ȃ������B���̂��߁A�ڋq���x���͒n��}�l�W���[�̎w���̎d������Ƃ����ʂ�����A�u�V���[�Y�A�h�o�C�U�[�v����̈�A�̎��i�擾�́A�ڋq���x����S�Ђœ��ꂵ�A����ɃX�L���A�b�v�����ڋq�����悤�Ƃ����ړI������B ���ł�40���قǂ̃V���[�t�B�b�^�[���a�����Ă���A�����i�K�łP�O�O���قǂ̃V���[�t�B�b�^�[��u���āA�ڋq�̔��Ɏ��g�ތv�悾�B �e�L�X�g���̃`�[���ɏ����Q�����Q�� �ڋq�̔��̃X�L���A�b�v�̑��i�K�ł���u�V���[�Y�A�h�o�C�U�[�v�B���̃e�L�X�g���́A��N�U������X�^�[�g���Ă���B���̗����グ�`�[���W���̒��ɁA�Q���̏����Ј����Q�������B���̈�l���V���[�Y�p���b�^�������X�i�����E�]�ː��j�̎R���v���q�X���i39�j�ł���B���N�œ���20�N�A�X���ɂȂ���10�N�ڂ��}���邪�A�V���[�t�B�b�^�[�F��҂ł��邱�Ƃ�A�r�b���X�܂̓X�������Ă����Ƃ��ɁA���[���v���[�C���O���̒n����ɂ܂ŏo�ꂵ�����т�����ꂽ�B �ڋq�̔��̃X�L���A�b�v�̑��i�K�ł���u�V���[�Y�A�h�o�C�U�[�v�B���̃e�L�X�g���́A��N�U������X�^�[�g���Ă���B���̗����グ�`�[���W���̒��ɁA�Q���̏����Ј����Q�������B���̈�l���V���[�Y�p���b�^�������X�i�����E�]�ː��j�̎R���v���q�X���i39�j�ł���B���N�œ���20�N�A�X���ɂȂ���10�N�ڂ��}���邪�A�V���[�t�B�b�^�[�F��҂ł��邱�Ƃ�A�r�b���X�܂̓X�������Ă����Ƃ��ɁA���[���v���[�C���O���̒n����ɂ܂ŏo�ꂵ�����т�����ꂽ�BA�S��60�y�[�W�̃e�L�X�g���Ј��̎�ō��ꂽ���A���̒��ŎR������͔̔��X�^�b�t�̃`�F�b�N�V�[�g�Â���Ȃǂ�S�������B�����ŏ����Ȃ�ł͂̃`�F�b�N���e�ɂȂ��Ă���B �u�l�C���̎g�p�Ɣ��̖т̐F�̊���A�j���Ј��ƈӌ����قȂ�܂����B�܂͐����ł��邱�Ƃ͓��R�ł����A�l�C�������Ă����ق����A���V�[�g��n���Ƃ��ȂǏ����q�ɂ͍D��ۂ�^���܂��B���̖т̐F���A�J���[�`���[�g�̃u���E���T�܂łȂ�A���q���܂ɑ��Ă͋��e�͈͂ł��B�܂��A�~��̗₽���\�t�@�[�Ƀu�����P�b�g��~�����Ƃ�A�~�j�X�J�[�g�̏����ɕG�|����p�ӂ��邱�Ƃ������ڐ��̃`�F�b�N���ڂł��v�ƎR���X���͘b���B �ڋq�́u�������A�m�F����v�����R�����X���߂�V���[�Y�p���b�^�́A��N����W�J���n�܂����V�ƑԂŁA���݂W�X�܂���B�t�@�~���[�u���̃t�����C�������A�`���_�ƑԂ��A�C�e�������i���āA�T�C�Y�Ɍ��݂��������Ă���A����͖��邭�A�����ڐ��ɗ������X�Â���Ɏ��g��ł���B�������X�������q���U�����߁A�V�K�ڋq����荞��ł���B�܂��A�����Ȏq��������Ղ�����ɂȂ��Ă���A�q�P���̓A�b�v���Ă���B�����ŎR�����S�����Ă���ڋq�́u���q���܂ɓ������A��Ɋm�F�����邱�Ɓv�Ƃ����B��������Ƃ́A�u�C���͂����Ƃő����ɂ��Ƃ����l�ɑ��āA�w��������Βɂ݂��Ȃ��Ȃ�܂��x�ƌ����̂ł͂Ȃ��A�w��ςł����ˁx�ƁA�܂�����̗���ɗ����Ēɂ����Ƃ��Ă����A���̒ɂ݂𗝉����Ȃ����b�����ׂ����ƍl���Ă��܂��v�Ɛ�������B  �R���X���͍�N�A�V���[�t�B�b�^�[�ɔF�肳��Ă��邪�A�����ł̒m���������ڋq�ɖ𗧂��Ă���B�u�Ⴆ�A����ؖ����̂��q���n�C�q�[�����͂������̐h����i���ė������Ȃǁw���̋N���������h���ł��傤�x�ƁA���ɂ݂𗝉����Ă����邱�ƂŁA���Â��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A���q����Ƃ��Ă͘b���Ă悩�����Ǝv���܂��v�B �R���X���͍�N�A�V���[�t�B�b�^�[�ɔF�肳��Ă��邪�A�����ł̒m���������ڋq�ɖ𗧂��Ă���B�u�Ⴆ�A����ؖ����̂��q���n�C�q�[�����͂������̐h����i���ė������Ȃǁw���̋N���������h���ł��傤�x�ƁA���ɂ݂𗝉����Ă����邱�ƂŁA���Â��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A���q����Ƃ��Ă͘b���Ă悩�����Ǝv���܂��v�B�܂��A�m�F�Ƃ́u���q���܂���w�E�H�[�L���O�V���[�Y���~�����x�ƌ���ꂽ�Ƃ��A�����T�C�Y�ƐF�����������ēn���̂ł͂Ȃ��A�w���A�ǂ�������ʂł͂��E�H�[�L���O�V���[�Y�ł����H�x�w���s�ł͂��܂����H�@���X�g�����ɍs����܂����H�x�ȂǂƁA���߂Ă�����̂�[���Nj����A�m�F���邱�ƂŁA���q���܂̊����ɂȂ��Ă������ƂɐS�����Ă��܂��v�Ƃ����B �ڋq��ʂ��Ă��q�̐����E���R�������H����ڋq�́A�R�O�O���ȏ�W�܂����֓��n��̓X���̑O�ŁA���[���v���[�C���O�̂������Ŕ��\���ꂽ�B�`���_�ɂƂ��Ă͍�������X�^�[�g�������ł��������A���Ă����j���X���̒��ɂ́u�������܂ł̐ڋq�́A��肷���ł͂Ȃ����H�v�u���ԓI�Ȗ�������A�������܂ł͂ł��Ȃ��v�Ƃ����悤�Ȕ������������Ƃ����B�u�V�i���I�͍��܂������A�����ăp�t�H�[�}���X�ł͂���܂���B����Ŏ��ۂɍs���Ă��邱�Ƃł����A�܂��܂����ׂ����Ƃ͂���A�ق��̓X�ł����ۂɎ��g��ł��炢�������Ƃ������܂����B���Ǝ�̃��[���v���[�C���O������A�����Ƃ��ׂ����Ƃ��������ƂɋC�Â��܂��v�B �����Ƃ��Ă̇��C�Â�����ڋq�̖ʂŁA�����̓X����O�ɁA���[���v���[�C���O�Ō������R���X���B����ł͐ڋq���w�������啔���͂Ȃ����A�X���ł̐ڋq��ʂ��āA���q���܂̐����L���`�����ڂ��������ƍl���Ă���B �R������̂悤�Ȏp���ł��q���܂Ɛڂ��邱�Ƃ́A�����ڐ��œX�Â���Ɏ��g��ł���V���[�Y�p���b�^�̑��X�܉������삵�������B���ƑԂ�30�X�܂̓W�J�����肵�Ă���A���̌���g�傷��v�悾�B�����ł͂l�c��ڋq�̓���ŁA�V���b�v�E�u�����f�B���O��}��l�����B �u�����{���ɂق����X�[�c�P�[�X�v������ �@�u�����́A�����ɂ��A�����̂��߂̃X�[�c�P�[�X�v����N�S���ɔ�������A�l�C���Ă�ł���B���s�ɐϋɓI��25�`30��O���̏����q�l����ړI�ɁA�n�ƈȗ����ƂȂ鏗���J���`�[�����������ꂽ�B���̃v���W�F�N�g���X�^�[�g�����͖̂�Q�N�O�̂Q�O�P�R�N�S���B�J�������o�[�́A���i���A�}�[�P�e�B���O�A���Y�A���ނȂNJe��������I�����ꂽ��菗���Ј��U�l�B��悩��s�꒲���A���ޒ��B�A���Y�A�o�q�܂ł��̂Â��肪�����ł��郁���o�[���W�߂�ꂽ�B �@�u�����́A�����ɂ��A�����̂��߂̃X�[�c�P�[�X�v����N�S���ɔ�������A�l�C���Ă�ł���B���s�ɐϋɓI��25�`30��O���̏����q�l����ړI�ɁA�n�ƈȗ����ƂȂ鏗���J���`�[�����������ꂽ�B���̃v���W�F�N�g���X�^�[�g�����͖̂�Q�N�O�̂Q�O�P�R�N�S���B�J�������o�[�́A���i���A�}�[�P�e�B���O�A���Y�A���ނȂNJe��������I�����ꂽ��菗���Ј��U�l�B��悩��s�꒲���A���ޒ��B�A���Y�A�o�q�܂ł��̂Â��肪�����ł��郁���o�[���W�߂�ꂽ�B�ŏ��ɁA�u����Ȃ��Ă��悢����g�����������{���ɂق����Ǝv���h�����p�X�[�c�P�[�X�����悤�Ɂv�Ƃ����w�����������B �܂��̓R���Z�v�g�Â��肩��X�^�[�g�B�U�l�̑I�������o�[�͂��ꂼ�ꃁ�C���̎d���������Ȃ���̃v���W�F�N�g�Ȃ̂ŁA�X�P�W���[�������������ւ����B����Ȃ�ƃ����`�~�[�e�B���O�ŁA���܂��܂Ȃ��Ƃ����肵�Ă������B�܂��A�J���`�[���ɂ͂����ă��[�_�[������Ȃ������B����́A�U�l�������̗���Ŏ��R�Ɉӌ����o�������A���s����̂����A�n�������A�S�����{���ɂق������̂Ƃ��ē��ꂷ��܂ł͐�ɐi�܂Ȃ��Ƃ����Ӑ}�����������߂��B �@�u���ꂼ��̕����̈ӌ����Ď������A����ł͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɩ������Ƃ����X����܂����B����ȂƂ��ɂ́A������x���_�́w�����{���ɂق����X�[�c�P�[�X�x������Ƃ������_�ɖ߂�悤�ɂ��܂����v�i�l�c�{�����i��敔�f�U�C�i�[�E�v�����q����j �R���Z�v�g���܂Ƃ߂�܂łɎ��Ԃ�������A�̔�����܂łɖ�50����̉�c���s�����B �@�u�����h�����u�g���m�s�v�i�n���g�FHave a�@�mice �sime�j�A�A�C�R����I�A�V���{����Z�p�`�Ɍ���B�I�̑���U�l�̃����o�[����C���[�W�����Z�p�`�̃V���{�����A���Z�p�`�ɂ��Ȃ������̂́A���ꂼ��̌���\�������������Ƃ���������肩�炾�B �@14�N�S���ɔ��������̂͂Q�^�R�F�B�J���[�ł̓s���N���͂������B�������s���N�Ƃ����C���[�W�����邪�A�^�[�Q�b�g�Ƃ��鏗���w�́A�s���N��背�b�h�̕��������₷���̂ł͂ƍl�������炾�B�@�\��f�U�C���̈�ЂƂɂ܂ŏ����ڐ����s���͂����B�{�̂̃J���[���ƂɈقȂ�I���W�i���̓����v�����g���A�����Ȃ�ł̖͂ڐ����B�v���10�{���̔��グ��B�����A�v���W�F�N�g�͑听�������߂��B���N�R���ɂ͐V�F�̃r�I���l�C�r�[������B �@�u���m�Â��肪���̂悤�Ɏn�܂��āA�ŏI�n�_�܂Ŋւ�ꂽ�̂͂ƂĂ��M�d�Ȍo���ł��B����̃��m�Â���Ɍ����Ă����Ǝ�����L�߂Ă��������v�u���m�Â���͋C���������߂�قǂɂ悢���̂��ł���Ǝ������܂����v�Ƃ������ʂɂȂ������B �u�n���g�v�͐V�����o�[�ɂ���āA��ꐢ��̂c�m�`���p���A����ɐi���������̂Â��肪�W�J����Ă���B  ���A���^�[�Q�b�g�ł̏��i�J���ɂ�������������E�햱������l�c�{�����́A�`�[��������ꂽ���R���A�����q�ׂĂ���B �u�o�b�O�Ƃ������̂Â�������Ă��铖�Ђł����A�e�P�w�i20�`34�܂ł̏����j�Ɍ����{���ɂق����Ǝv���Ă��炦�鏤�i�������Ă��邩�^��������Ă��܂����B�e�P�w�͎u�������݂ɂ������̂��Ă��������œ���w�ł��B�{���Ƀ��A���^�[�Q�b�g��������͓̂�����Ȃ̂ŁA���Ђ̎�菗�q�Ј���I�����āA���̃v���W�F�N�g���X�^�[�g�����܂����v�B �^�����e�[�}�́A���A���ɊC�O���s�p�̃o�b�O�ŁA�u�����{���ɂق����X�[�c�P�[�X�v�����ł���B�u����Ȃ��Ă������v�Ƃ��������B�Г��ł����̃v���W�F�N�g�ł͂Ȃ��A�����{�������e�����̃g�b�v�ɋ������X�^�[�g�����J���`�[���������B �u�Г��Ō��ɂȂ�ƁA���������Ȃ�s���N�����悤�A�A�C�R�����I�ł͉����Ȃ��̂ł́A���̃f�U�C���͂ǂ��Ȃ̂ȂǁA���܂��܂ȏ��ɘf�킳��A���ǁA�ޏ������̖{���ɂق������i���ł��Ȃ����ɂȂ�ƍl��������ł��v�B �@�����{�������g�͊J���Ɉ�،��o�������Ȃ������B 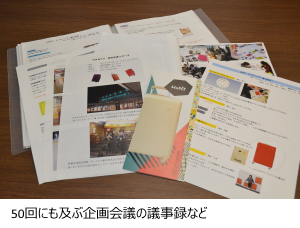 �u�ޏ������͎��Ј������łƂĂ��s���������Ǝv���܂��B�c���^������ƁA�s�����藈���肵�Ė����Ă��镔���������܂����B������w�{���ɔ���Ȃ��Ă��悢�ł����x�Ƃ������Ƃ��Ă��܂����v�B ���̂��тɔ���Ȃ��Ă��悢�ƔO�������A��������Ă���Ǝv��ꂽ�Ƃ��ɂ́u�{���ɂق����X�[�c�P�[�X������Ȃ����v�Ə��������B �ޏ������������������Ƃ́A������̐l�����̗�݂ɂ��Ȃ�A�܂��h���ɂ��Ȃ����B�v���W�F�N�g���听�������߂��̂́A�������������������{�����̑��݂ƁA���̂Â���������Ă�܂Ȃ����������̗͂ɂ����̂��낤�B |
||||||||||||