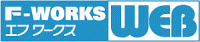 |
|
||||
  |
||||
 「ファッショナブルな靴磨き」を確立し、職人の地位を高めるシューシャイン職人として高品質で量をこなす  カウンターでパリッとしたスーツを着て、かっこよく靴を磨く。カウンター越しに軽妙なトークでお客を楽しませる。こんなスタイルを確立し、シューシャインの世界を広げてきた長谷川裕也さん。そのスタートが東京駅前の路上靴磨きだった。 「11年前に東京・青山にお店を持ったのは、時間をかけて磨きたかったのと、遠くからわざわざ靴を磨いてもらいにくるという価値観をつくりたかった」と話す。 顧客は、クリーニング感覚で磨きに出すエグゼクティブの人々と、靴磨きが大好きな人たち。後者には同業者もいて、学びたい人たちも多い。長谷川さんは「これはどういう作業で、何のためにしているのか」をていねいに説明していく。 「大切にしているのは、一つひとつの工程をきちんと行うことです。もう一つは速さです。私たちは芸術家ではなくて職人です。たくさんの量を高いレベルでこなしていくことが重要で、速さと品質はイコールです」。 こだわりは、日頃使うシューケア用品にも現れている。クリームは化粧品会社、クロスは染物屋と、それぞれベストな企業とコラボレートしているオリジナル商品だ。    後進の指導では技術と接客を重視  長谷川さんが一躍有名になったのは、2017年にロンドンで行われた靴磨き世界大会で優勝したことだった。今年9月に伊勢丹の「靴博」で行われた世界大会に出場、再び優勝を飾った。 日本のシューシャイン界のトップであり、入門を希望してくる人も少なくない。現在、ブリフトアッシュには8人の職人がいる。ここでは「職人の地位を上げる」ことを目標に、磨きの技術とともに、接客も重視することを教えている。「うちはビジネスホテルではない、おもてなしのできる一流ホテルなんだ」という長谷川さんの言葉に、その自負が現れている。 シューシャインのすそ野を広げるために、長谷川さんは店舗経営を拡大している。また、 10月からは障害者施設と組んで、スタッフたちに靴磨きを教えるプロジェクトも始めた。 ファッションとしての靴磨きを確立した長谷川さんは、まだ30代。長谷川さんも日本のシューシャインも、まだまだ伸びていく。    シューケアの延長としてリカラーを楽しむ靴の引き立て役として多彩な染め替えを行う 藤澤宣彰(のぶあき)さんが靴の染め替え(リカラー)に出会ったのは、15年前のことである。フランスのシューケアメーカーの人と出会い、初めてリカラーを知る。そこで基礎を学び、後は独学で方法を開拓した。 それまで務めていたワールドフットウエアギャラリーで、顧客の靴や古くなった靴を染めていた。その後、コロンブスに転職。そこでクリームの染料やタンナーの塗料など個人には使えないものを知り、染料のつくり方も学び、8年後に独立した。 靴のリカラーのオーダーには、「シミや傷がついてしまったから」という修理に近い依頼と、「ほかのカラーにして気分を変えたい」「このデザインの別のカラーがほしい」という2タイプがある。 「こだわりは、染めはあくまで靴の引き立て役だということです。ライトブラウンの靴を濃い茶に染め替えるのにも、『染め替えたんだな』ではなく『いい色の革だな』と言われたい。それが理想です」。 手法は多い。つま先のぼかし染め、マーブル調、色を落としたように見せるアンティーク調、グラデーションなど。お客はサンプルを見て望むタイプをオーダーする。  ワークショップで染めの世界を広げる  ここ数年、リカラーのニーズは高まり、シューケアの延長として楽しむ人が多くなっている。藤澤さんは多くのワークショップを開き、プロの靴職人からエンドユーザーまでの人々に、リカラーの楽しさを教えている。 今後は、自社企画で国内工場に白いスニーカーを作ってもらうことを考えている。最初から色がついていては、明るいカラーに染められず、自分の色を作ってトライしたい、というワークショップ参加者の希望に応えるためだ。 藤澤さんは、工場の外で「個人がリカラーを楽しむ」道を開いたパイオニアである。その文化は日本でまだ始まったばかりだ。染めの世界は、深くまた広い。成長していく未来が楽しみな分野でもある。   豊富な知識とテクニックで、臨機応変にケアを提案
シューケア用品のコロンブスは、多くのシューシャイニストを抱える。この中でトップクラスの技術を持つのが、三橋弘明さんだ。 |
||||
 |